高等教育質保証機関の国際ネットワーク(INQAAHE)隔年総会2025に出席しました
令和7年5月13日(火)から15日(木)にかけて、高等教育質保証機関の国際ネットワーク(INQAAHE:International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education)の隔年総会が東京で開催され、当機構から服部機構長をはじめ、光石理事、研究開発部教員、国際課職員が出席しました。
INQAAHEは総会とフォーラムを隔年で交互に開催しており、本年は総会が開催されました。今回は、“The Big Bang Theory: The Quality Assurance Paradigm Shift」”(ビッグバンセオリー: 質保証のパラダイムシフト)をテーマに、基調講演、パネルディスカッション、分科会及び会員総会が行われました。
総会では、急速な技術革新、人口構造の変化、新たな教育形態の出現等、現代社会における急激な変化に対応する高等教育の質保証のあり方について、世界各国からの登壇者・発表者から知見や実践が共有され、活発な意見交換が行われました。
基調講演では、「質保証は、高等教育におけるイノベーションや柔軟性、そして社会からの信頼を支えるために、絶えず進化していく必要がある。」との見解が示されました。また、「これまでの「基準への適合性」を重視する視点から、高等教育機関の「継続的な質の向上」を促す視点への転換が求められている。」との主張がなされました。
また、米国で行われた調査結果を踏まえ、各分野で進行する変化や必要とされるツールに関する知識の教授(teaching)、アカデミック・インテグリティに関する指導、そして、雇用主が求めるAI人材の育成が求められていることが強調されました。さらに、AIに関する高等教育機関の質保証に向けたチェックリストも紹介されました。
その他にも、アフリカにおける質の高い高等教育の提供に向けて、AIを教育の現場で活用している事例の紹介がありました。また、学びや資格の多様化や国境を越えた教育の提供が進展する中、学生が高等教育での学びで得た資格の円滑な承認を実現するために、各ステークホルダーが果たすべき役割等についての講演もありました。
分科会では、機構は、覚書締結機関と共同で2件の発表を行いました。1件目では、戸田山研究開発部長がフランス研究・高等教育評価高等審議会(Hcéres)と共同で「Non-university education – specific pathway, specific EQA? The examples of “grandes écoles/daigakko” in France and Japan」という演題のもと、フランスのグランゼコール及び日本の大学校といった、それぞれの国における「非大学型教育(non-university education)」の制度とそれに対する質保証機関の役割についての発表を行いました。
2件目では、堀田客員教授が、中国教育部教育質評価センター(EQEA)及び韓国大学教育協議会(KCUE)と共同で「“Common Quality Assurance Standards” for inter-university exchange with quality assurance within the broader Asian region」の演題で発表し、3機関が共同で策定した「キャンパス・アジア共通質保証プロジェクト」における「共通質保証基準」について紹介しました。また、参加者に対して、「共通質保証基準」の活用等に関するアンケートを行うなど、インタラクティブなセッションを設け、参加者と活発な意見交換を行いました。
今回の総会には世界各国・地域から約270名の高等教育・質保証関係者が参加しました。当機構の参加者は分科会での発表に加え、各国・地域の質保証機関や高等教育機関との懇談も活発に行いました。これにより、当機構の活動を発信するとともに、質保証に関する情報交換を行う貴重な機会となりました。
※INQAAHEについて:
INQAAHEは、1991年に設立され、高等教育の質の評価、改善及び維持に関する理論や実践について、情報収集及び情報提供を行うことを目的とする国際ネットワーク。当機構は2001年7月より正会員として加盟している。

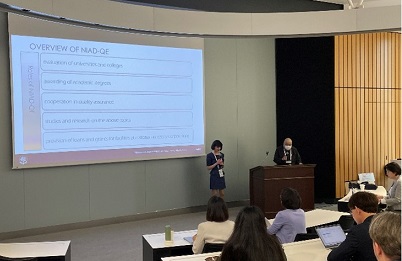
会場の様子 戸田山研究開発部長とHcéresとの共同発表の様子
