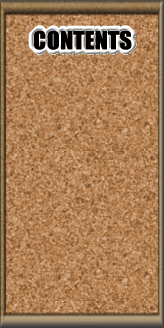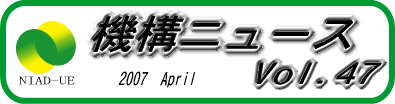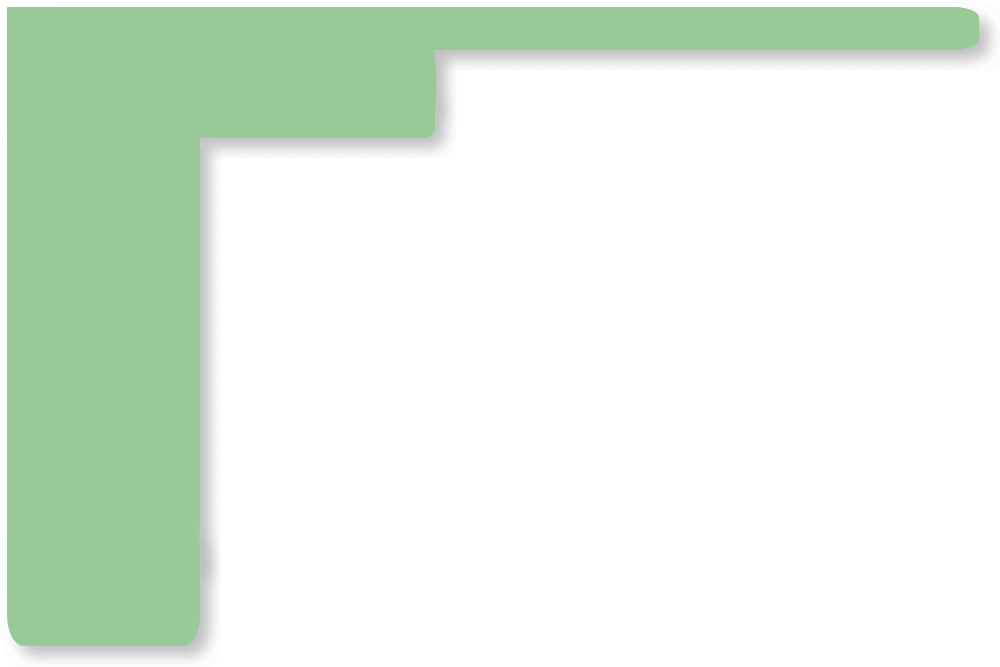|
| |1|2|3|4|5| |
| ○ |
シンポジウム「ユニバーサル時代の学位と学習履歴」の開催 |
|
平成19年3月27日(火)に「ユニバーサル時代の学位と学習履歴」と題したシンポジウムを当機構竹橋オフィスにおいて開催いたしました。 |
|
|
|
高等教育への進学率が50%を超えるユニバーサル段階では、学生が一つの大学にとどまらず、複数の機関を移動して学習を続ける形が増えると想定されます。このような学習行動の変化は、大学にどのような影響を与えるでしょうか。従来の大学は、一貫した在学とそれにもとづく教育課程の体系的な履修を前提として、学生に対する教育と学位の質を保証してきました。しかし学生が編入学、転学によって機関を移り、あるいは中途退学や卒業後に再入学する場合に、大学の教育課程は断続的に履修されることになります。日本でもディグリー・ミル(偽学位工場)に対する問題意識が高まりつつありますが、学位の認証と学習履歴の認定(単位認定)は体系的な学修を保証するうえで重要であるにもかかわらず、インターネットを通じて配信される教育プログラムや営利大学の登場などによって、その作業にはきわめて多くの労力と時間を要するようになっています。 |
|
このような問題に先駆的に取り組んできたのがアメリカです。アメリカでは関係者の自発性にもとづいて、さまざまな仕掛けが設けられてきました。その経験は日本にも有益な示唆を与えるにちがいありません。こうした関心から、学位審査研究部ではアメリカの関係者をお招きして、2007年3月27日(火)にシンポジウム「ユニバーサル時代の学位と学習履歴」を開催しました。ご登壇いただいたのは、ジェリー・サリヴァン氏(全米学籍登録担当・アドミッションオフィサー協会)、ジェフリー・M・タナー氏(全米学生クリアリングハウス)、モニク・L・スノーデン氏(テキサスA&M大学)の3名です。 |
|
シンポジウムの前半では、学生移動に伴う諸問題に関して、(1)科目の等価性を判断し、単位認定を容易にするために全国的な大学職員協会(AACRAO)が開発している仕組み、(2)学生・卒業生の取得学位、学習履歴、在籍記録の確認を可能にする総合的なデータバンク、(3)州内の高等教育機関間で学籍登録の管理を支援する電子データ交換システム、についてそれぞれ講演していただきました。 |
|
続くパネル・ディスカッションでは、金子元久教授(東京大学大学院教育学研究科長)の司会により、アメリカの経験をふまえて日本の課題が議論されました。講演内容に刺激を受けた参加者から多数の質問が寄せられ、個人情報の管理に関する問題、日本における全国的なデータベース構築の可能性など、パネリストとの間で活発な意見交換が行なわれました。
パネリストの発言の中では、アメリカの全国的な大学職員協会や非営利機関が開発してきたデータバンクは大学および学生・卒業者の支援が一義的な目的であり、授業科目の基準設定や画一化を意図しているのではないこと、大学はそれぞれ使命に応じて教育課程を編成しているのであり、転・編入学者の学習履歴を審査して自大学の教育課程の一部(既修得単位)と認めるか否かの判断はあくまで各大学に委ねられるべきであること、さらに単位認定や学位の認証は事務的な作業と捉えられがちだが、個々の修得単位が表しているのは教員と学生との間で行なわれた教育活動の成果であることを忘れてはならないことが強調され、40人近い参加者に深い印象を与えました。 |
|
シンポジウムの成果は、機構が刊行する学術誌『大学評価・学位研究』に論文等として発表される予定です。 |
|
(学位審査研究部 吉川裕美子) |
|
|
|
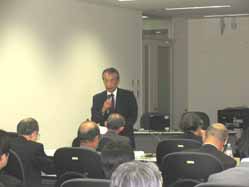 |
|
 |
| 「木村機構長による開会の挨拶」 |
|
「パネル・ディスカッションの様子」 |
|
|
|
|
【開催日時・プログラム】 |
|
| 1.主 催 |
大学評価・学位授与機構(学位審査研究部) |
|
| 2.日 時 |
2007(平成19)年3月27日(火)13:00〜17:30 |
|
| 3.場 所 |
大学評価・学位授与機構竹橋オフィス11階会議室 |
|
| |
(東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター11階) |
|
| 4.言 語 |
同時通訳つき 日本語・英語 |
|
| 5.プログラム |
|
|
| (1)開会挨拶 |
木村 孟 (機構長) |
13:00 |
| (2)趣旨説明 |
吉川 裕美子(学位審査研究部 助教授) |
13:10〜13:40 |
| (3)講演 |
|
|
| |
「アメリカ高等教育における履修単位の移動プロセス」 |
13:40〜14:20 |
| |
ジェリー・サリヴァン Jerry Sullivan |
|
| |
(全米学籍登録担当・アドミッションオフィサー協会(AACRAO)常務取締役Executive Director) |
| |
|
|
| |
「ナショナル・ステューデント・クリアリングハウス:背景とサービス」 |
14:20〜15:00 |
| |
ジェフリー・M・タナー Dr. Jeffery M. Tanner |
|
| |
(全米ステューデント・クリアリングハウス 副社長Vice President) |
| |
|
|
| |
「学生登録の管理と電子データ交換」 |
15:00〜15:40 |
| |
モニク・L・スノーデン Monique L. Snowden |
|
| |
(テキサス A&M 大学 学籍登録調査・技術 ディレクターDirector) |
| |
|
|
| |
休 憩 |
15:40〜16:00 |
| (4)パネル・ディスカッション |
16:00〜17:30 |
| |
ジェリー・サリヴァン Jerry Sullivan
ジェフリー・M・タナー Jeffery M. Tanner
モニク・L・スノーデン Monique L. Snowden
吉川裕美子
司会 金子元久(東京大学大学院 教育学研究科長) |
|
| (5)閉 会 |
橋本 弘信(学位審査研究部長) |
17:30 |
| |
| お時間に余裕のある方は、18時からのレセプションにもご参加ください。 |
| 会 場 如水会館 3階 けやきの間 |
| |
| このシンポジウムは、科学研究費補助金による研究(「学士取得過程の多様化に対応した単位認定と学士の質保証に関する日米欧の比較研究」基盤研究(B)研究代表者 吉川裕美子)の一部として企画するとともに、当機構の学位授与事業と密接に係わる内容であるため、機構(学位審査研究部)の主催として実施するものです。 |
|
|
  |